銀行とかに預けると普通預金とかは、1金融機関あたり元本は1000万円まで補償…と思っていました。
が、
どうやら、決済用預金にすると、1000万円以上も保護されるらしい。
皆さんご存じでした?

預金保険制度とは
預金保険制度とは、金融機関が預金保険料を預金保険機構に支払い、万が一、金融機関が破綻した場合に、一定額の預金等を保護するための保険制度のこと。対象となる預金に関しては、自動的に手続きがなされるため、預金者は預金保険については特に手続きをする必要はない。
預金の分類について
以下の通り分類されます。
預金保険制度の対象となる預金等
- 決済用預金:当座預金・利息の付かない 普通預金 等
- 一般預金等:利息の付く 普通預金・定期預金・定期積金・元本補填契約のある金銭信託 (ビッグ等の貸付信託を含む) 等
預金保険制度の対象外となる預金等
- 外貨預金、譲渡性預金、無記名預金、架空名義の預金、他人名義の預金 (借名預金)、金融債 (募集債及び保護預り契約が終了したもの) 等
→これらは保護対象外となります。
※ 当座預金とは、企業や個人事業主が利用する、主に手形や小切手の支払いに使われる口座のこと。
※ 利息のつかない普通預金っていうのは、いわゆる「無利息型普通預金」です。

なすがままに普通預金口座を作ったら、利息のつく普通預金になっているはずなので、一般預金等に該当する口座を作っている方が多いのではないでしょうか。
自分は気にしたこともなかったけど、そういえば、口座作るときに利息の有無を選ぶの、選択肢としてはあったような…?
預金保険制度の対象となる預金の保護の範囲は?
決済用預金
…全額保護
一般預金等
…金融機関ごとに預金者一人当たり、元本1000万円までと破綻日までの利息等が保護
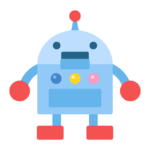
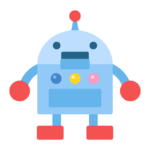
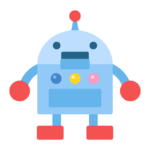
決済用預金は全額保護って書いてある!!
1000万円超えたら私の貯金も全額保護してほしい!
決済用預金って簡単に作ることできるの?
決済用預金とは
まず、決済用預金の定義。
決済用預金とは、
① 決済サービスを提供できること
② 預金者が払戻しをいつでも請求できること
③ 利息がつかないこと
という3要件を満たす預金で、当座預金、無利息の普通預金、別段預金の一部がこれに該当する(預金保険法第51条の2参照)。
ということで、「利息の付かない普通預金」は、
預金保険制度により全額保護される、無利息の普通預金
のこと。
無利息型普通預金 (決済用預金) のデメリット
普通預金とほぼ同じ扱いになるけれど、金利がつかないというデメリットがある。
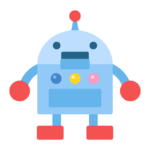
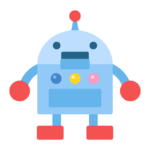
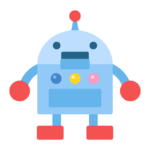
デメリット…。
でも今って、存在すら忘れてしまいそうな低金利だから、
自分の貯金程度なら、あまりデメリットって感じもしない…。
決済用預金口座を使うには
決済用預金を利用できる銀行と、そうでない銀行があります。
銀行によりますが、一般的に「利息の付かない普通預金 (決済用預金)」を使用するには、新規で口座を作るか、「利息のつく普通預金」口座から「利息の付かない普通預金 (決済用預金)」口座に切り替えるという方法があります。
また、銀行によって若干手続きに違いはあるかもしれませんが、有利息から無利息、無利息から有利息、いずれの切替時にも、届出書に必要な書類に貼るための 収入印紙200円 が必要 とのことです(ネット銀行の場合は不要の場合もあり)。
収入印紙を用意しさえすれば、簡単にお手続きできるみたい。



先日某メガバンクでお手続きしてみました。
ネット銀行ではないけれど、インターネットバンキング経由で、
自宅から、収入印紙なし、手数料なしで手続きすることができました✨
なお、銀行によっては、一度切り替えたら、元に戻すことができないところもある らしいです。例えば2022年8月1日現在、三井住友銀行は、「決済用普通預金を、有利息の各種普通預金にお切り替えいただくことは、原則としてできません。」とありました。利用を検討する場合は、対象の銀行の規定をしっかり確認した方がよさそうです。
最後に
ということで、今回は決済用預金の話でした。
低金利の今は、全額保護の決済用預金を利用するのもアリかなと思った次第です。
金融庁のHPを見ていると、がっつり「全額保護」って書いてあるから、大丈夫だとは思うのですが、預金保険法第51条の2 (決済用預金に係る保険料の額) とかを見ていると、本当に100%保証されるのかよくわからないけど…という疑問は少し残る…。
一つの銀行に預金を固めるより、複数の銀行をうまく使いながら、必要に応じて決済用預金を利用したらいいのかもしれないと思いました。
あ、1000万円超えていなかったら、気にしなくていいんですけどね。
参考:金融庁 預金保険制度

